🕒 読了目安:8分
💡東京都水道局の令和5年度決算・収益構造・設備投資・将来の更新需要やDX戦略を実務目線で整理。地方公営企業会計の学習にも最適です。
― 首都の水道を支える巨大インフラの“お金の流れ”をやさしく解説 ―
「東京の水道って黒字なんですよ」。
そう聞くと少し意外に思うかもしれませんよね。実は東京都水道局は、全国でもトップクラスの収益規模を誇る“安定経営の公営企業”なんです。この記事では、その財務の中身と、これからの水道の未来を、少し肩の力を抜いて見ていきましょう。
1. 財務の現状:実はかなり“堅実な黒字経営”
まずは足元の数字から。
東京都水道局の最新決算(令和5年度決算概要)を見ると、営業収益は約3,244億円、純利益は約200億円。
このスケール感、さすが首都の水道ですよね。
主な収入はもちろん「水道料金」。
給水収益は約2,827億円で、前年より少し増えています。猛暑で水の使用量が増えたことや、経費をしっかり抑えたことが黒字の要因です。
しかも、一般会計(いわゆる都の税金)には頼らず、完全な独立採算制で運営しているのが東京都水道局の強み。
稼いだ利益はそのまま、老朽化した設備の更新や災害対策のために積み立てているそうです。
“黒字=利益を出すため”ではなく、“将来への備え”という感覚なんですね。
2. 投資の中身:見えないところにこそお金をかける
東京都水道局のすごいところは、「派手な建設」ではなく、“見えない投資”をしっかりやっている点です。
たとえば、令和5年度の投資額はおよそ1,800億円超。
そのうち、
- 浄水場などの施設更新:約200億円
- 配水管の更新・耐震化:約1,600億円
という内訳でした(出典:東京都水道局 事業概要2024)。
都内の配水管は約27,600km。地球の半周以上です。
この長大なネットワークを安全に保つには、日々のメンテナンスと計画的な更新が欠かせません。
「地味だけど一番大事な投資」。それが水道事業なんですよね。
3. 料金と財政バランス:実は“全国平均レベル”
「東京の水道料金って高いんじゃないの?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
ところが、実際は全国平均とほぼ同じなんです。
総務省の調査(上下水道料金調査2024年度版)によると、
東京23区の一般家庭の上下水道料金は年間約6万円。
全国平均が6.1万円ほどなので、むしろ“ちょっと安い”部類に入ります。
さらに驚くのは、1980年代以降ほとんど値上げしていないという事実。
それで黒字を維持しているのですから、経営の安定感は抜群ですよね。
ちなみに2025年夏には、東京都の支援で水道基本料金が4か月間無償化される予定です(出典:東京都「水道基本料金の無償化について」)。
都が事業会計に補填する形なので、水道局の経営に直接の影響はありません。
生活支援と公共サービスの両立、まさに“行政と企業のいいとこ取り”ですね。
4. 将来性①:これから訪れる「更新の波」
どんなに丈夫な水道管でも、永遠に使えるわけではありません。
高度経済成長期に整備された管路が、今まさに更新のタイミングを迎えています。
現状の更新スピードだと、すべての老朽管を取り替えるのに130年以上かかるともいわれています(出典:東京都会計局『公営企業決算報告2024』)。
このままでは更新が追いつかない、というわけです。
そこで東京都水道局は、“壊れる前に取り替える”予防保全型の考え方にシフト。
AIで管の劣化度を分析し、更新の優先順位をつける仕組みを導入しています。
データをもとに賢く投資する——まさに「スマートな公共経営」って感じですよね。
5. 将来性②:スマートメーターとDXの力
もうひとつ注目したいのが、デジタル化(DX)の動きです。
東京都水道局は2024年度までに13万個のスマートメーターを導入し(出典:東京都水道局「スマートメーター実証事業」)、2030年代には全世帯での導入を目指しています。
これが実現すると、検針作業は自動化され、漏水の早期発見や利用データの分析もできるようになります。
すでに「東京都水道局公式アプリ」では、検針結果や料金をスマホで確認できるようになっていて、利用者数は200万人を突破しました(出典:東京都水道局「お客さまサービス向上の取組」)。
「水道ってアナログな業界でしょ?」というイメージは、もう昔の話。
東京水道は今、データを活かすインフラ企業へと進化している最中なんです。
6. 将来性③:災害にも気候変動にも強い“レジリエント水道”へ
地震、豪雨、猛暑——。
東京の水道は、さまざまなリスクと向き合っています。
その中で、東京都水道局は耐震継手管の導入率99%超という高水準を実現(出典:東京都水道局「災害に強い水道」)。
主要貯水池や送水幹線の補強も進み、災害時の断水リスクを大幅に減らしました。
さらに、気候変動による渇水リスクにも備えています。
東京都の水源の約8割を占める利根川・荒川水系では、上流ダム群との広域連携を強化中です(出典:東京都水道局「水源地域の保全」)。
節水型機器の普及や再生水の活用など、資源の多様化にも動きがあります。
災害にも、気候変動にも負けない。
そんな“レジリエント水道”を目指す姿勢が、今の東京都水道局の大きな特徴なんです。
まとめ:東京水道の未来を一緒に考えてみよう
- 営業収益3,000億円超の安定黒字
- 設備更新と耐震化に年間2,000億円投資
- 料金水準は全国平均並み
- スマートメーターなどDXが進行中
- 災害・気候変動への備えも強化中
こうして見ると、東京都水道局は「公共×企業」のバランスがとれた存在ですよね。
安定経営を土台に、次の時代の課題へ一歩ずつ進んでいる。
そんな姿勢は、地方の公営企業にとっても大きなヒントになると思います。
次回は、東京都水道局が抱える課題と、大阪市など他都市との比較を通して、
「これからの水道経営」を一緒に考えてみましょう。
📚 参考資料一覧
- 東京都水道局「令和5年度決算概要」
- 東京都水道局「東京水道経営プラン2021」
- 東京都会計局「公営企業決算報告」
- 総務省「上下水道料金調査 2024年度版」
- 東京都水道局「スマートメーター導入実証事業」
- 東京都「水道基本料金無償化について」(都政発表 2025年3月)
- 東京都水道局「災害に強い水道」
- 東京都水道局「水源地域の保全」


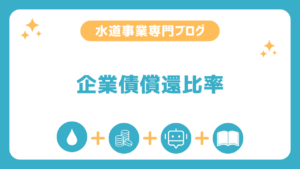

コメント