🕒 読了目安:8分
💡 この記事はシリーズ第2回です。
第1回「東京都水道局の財務状況と将来性」では、黒字経営の仕組みとDX化の動きを解説しました。
今回は、東京都水道局が直面する“見えない課題”と、大阪市水道局など他都市との比較から、首都の水道経営のリアルを探っていきましょう。
― 黒字の裏にある静かな課題と、日本最大の水道が目指す未来 ―
「東京の水道って安定してるよね」と言われることが多いですが、実際には静かな課題がいくつもあります。
老朽化、財政の持続性、技術者不足、そして気候変動。
どれも長期的には避けて通れないテーマです。
この記事では、そんな“首都の水道の裏側”をのぞいてみましょう。
1. 老朽化という長期リスク:更新のスピードが追いつかない
東京都の水道管は、総延長約27,600km。
その多くが高度経済成長期に整備され、すでに50年以上が経過しています。
現在の更新ペースでは、すべての老朽管を取り替えるのに130年以上かかるという試算もあります。
この数字、ちょっと驚きますよね。
もちろん、水道局も手をこまねいているわけではありません。
AIで管路の劣化度を分析し、破損リスクの高い区間から優先的に更新を進めています。
「とりあえず壊れたら直す」ではなく、“壊れる前に替える”。
こうした予防保全型の管理に舵を切っているのが今の東京都水道局です。
ただ、それでも更新投資は年間で1,000億円を超えます。
コストを抑えながら、どう持続的に更新を進めるか——これは今後の経営課題の中心になっていくでしょう。
2. 財政の持続可能性:黒字の裏にある“静かなプレッシャー”
東京都水道局は黒字を続けていますが、その裏にはプレッシャーもあります。
一番の要因は「人口動態」と「需要の変化」です。
東京都の人口はこれまで増加傾向でしたが、長期的には減少に転じる見込みです。
さらに節水機器の普及もあり、一人あたりの水使用量は年々減っています。
つまり、収入の柱である水道料金が伸びにくい状況なんです。
一方で、老朽化や耐震化の費用は確実に増えていく。
黒字を維持するためには、業務効率化や企業債(借入)の活用など、経営の工夫が欠かせません。
東京都水道局はこれまで、料金を据え置きながらも黒字を確保してきました。
でも今後、設備更新のピークが来れば、料金改定の検討が避けられない局面も来るかもしれません。
「値上げをどう説明するか」は、公営企業経営における最大の政治テーマのひとつですよね。
3. 人材と技術継承:人の確保が“次の危機”
どんなに設備が整っていても、結局それを動かすのは“人”です。
ところが、ここが静かに危機を迎えています。
東京都水道局では、熟練技術者の大量退職期が近づいています。
高度経済成長期に採用された世代が一斉に定年を迎えるため、技術の継承が課題になっているんです。
これに対して局は、若手採用と研修体制の強化を進めています。
OJTに加えて、退職技術者を再雇用して教育係として配置するなど、技能伝承の仕組みを整えています。
とはいえ、自治体全体で人材獲得競争が激化しており、「採用の難しさ」は東京とて例外ではありません。
AIやセンサーを活用した業務の省人化も進めていますが、やはり現場を支える人の力は欠かせません。
水道事業の持続性は、設備だけでなく“技術の継続性”にもかかっている。
そう感じますよね。
4. 気候変動リスクと水資源のゆくえ
ここ数年、夏の渇水ニュースを耳にする機会が増えました。
東京都の水源の約8割は利根川・荒川水系にありますが、近年の降雨パターンの変化で、渇水リスクや水質悪化リスクが指摘されています。
東京都水道局はこのリスクに備え、
- 上流ダムとの連携強化
- 雨水・再生水の活用
- 節水機器の普及支援
といった多面的な対応を進めています。
また、令和6年度には村山上貯水池の堤体補強を完了し、都内主要貯水池すべてで耐震化を達成しました。
気候変動は一朝一夕で解決できるテーマではありません。
でも、東京水道は少なくとも“備える力”を着実に高めているといえるでしょう。
5. 他都市との比較:大阪市水道局と見比べると見えてくるもの
では、日本で二番目に大きな水道事業、大阪市水道局と比べるとどうでしょうか。
| 指標 | 東京都水道局 | 大阪市水道局 |
|---|---|---|
| 給水人口 | 約1,400万人 | 約266万人 |
| 年間給水量 | 約15.5億m³ | 約4.4億m³ |
| 営業収益 | 約3,200億円 | 約520億円 |
| 料金水準(家庭平均) | 年6万円前後 | 年4.6万円前後 |
| 管路延長 | 約27,600km | 約5,200km |
こうして見ると、東京のスケールの大きさが際立ちます。
一方で、大阪市はコンパクトなエリアで低料金を維持しており、経営効率化を重視する傾向が強いです。
また、組織の形も対照的。
東京都水道局は“都直営の広域経営”で、すでに統合型モデルを確立。
大阪は近年、府内企業団への統合を進めています。
つまり東京は「すでに広域化済み」、大阪は「広域化を進めている途中」という構図なんですね。
それぞれの強みを比べてみると、
- 東京:財務体力と投資力で先進技術を導入
- 大阪:低料金と運営効率を重視
という“経営哲学の違い”が見えてきます。
どちらが正しい、ではなく、地域の状況に合わせた最適化。
公営企業経営の面白さって、まさにここにありますよね。
まとめ:黒字でも、安心しすぎないことが大切
今回見てきたように、東京都水道局は黒字でありながら、
老朽化・人材・気候変動という大きな課題を抱えています。
これらは「いま赤字じゃないから大丈夫」とは言えない、静かに進行するリスクです。
とはいえ、東京水道はそれらの課題に真正面から取り組んでいます。
予防保全、DX、広域連携、人材育成——。
一歩ずつ、次の時代に備えている姿勢が見えてきます。
黒字だからこそ、備える余裕がある。
それが、首都の水道が持つ最大の強みかもしれませんね。


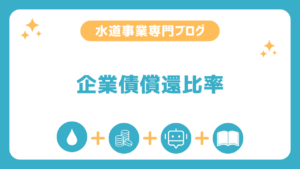

コメント