📘この記事の概要
- 読了時間:約10分
- 一言サマリー:なぜ水道事業が「公営」であるのかを、法制度・経済性・公共性の3つの視点から解説。民営化との違いや海外の再公営化動向も交えて、自治体経営の原理をコラム調で読み解きます。
1. リード:蛇口の向こうにある“公共”の物語
あなたが蛇口をひねってコップに水を満たす。その透明な一杯の裏側には、目に見えない何十年もの努力があります。
日本の水道は、ほぼすべてが自治体による公営。では、なぜ民間ではなく、あえて公営で運営されているのでしょうか?
「民間のほうが効率的では?」という声を耳にすることもあります。しかし水道は単なるビジネスではありません。社会全体の“安心と衛生”を支える公共基盤なのです。
この記事では、法制度・経済性・公共性の3つの柱をもとに、水道事業が公営である必然を読み解きます。
2. 背景:なぜ今「公営か民営か」が問われているのか
水道の経営を巡る議論は、近年いっそう現実味を帯びています。
背景には、人口減少・施設老朽化・技術職員の減少という“三重苦”があります。
地方の小規模自治体では、給水管1kmあたりの利用者が少なく、維持費が都市部の数倍にも及ぶことがあります。収益は減るのに費用は増える。結果、経営の持続性が課題となり、「民間活力の導入」が注目されるようになりました。
しかし、ここで立ち止まる必要があります。
水道は“命に関わるサービス”であり、一度止まると地域全体の生活や衛生が崩壊します。電気や通信が止まるのと次元が違うのです。
つまり、水道は「商品」ではなく「社会的権利」。その責任を果たす主体として、行政=自治体が担うことが制度の根幹になっています。
民営化の議論は「公営の限界」ではなく、「公営の中でどう効率化するか」という問いへと進化しつつあります。
3. 法制度の視点:なぜ市町村が担い手なのか
水道が公営である最大の理由は、法律そのものにあります。
水道法第6条(出典:e-Gov法令検索「水道法」)には次のように明記されています。
「水道を設置する者は、市町村その他の公共団体とする。」
つまり、法律の原則として、水道は公共団体の仕事です。
この条文の背景には、戦後の衛生行政があります。コレラや赤痢などの感染症が猛威をふるっていた時代、清潔な水の供給は国民の命を守る行政責任とされました。
水道法第1条(出典:環境省「水道法関連法規」)では、目的を「国民の生活の安定と公衆衛生の向上」と定めています。
つまり、水道は単なるインフラではなく、衛生政策の一環として誕生した公共制度なのです。
民間委託やPPP(官民連携)はあくまで補完的な手段であり、最終責任は自治体が負う構造になっています。
4. 経済性の視点:なぜ競争が成り立たないのか
経済学的に見ると、水道は「自然独占型事業」です。
配管や施設の整備には莫大な投資が必要で、複数事業者が並立すると非効率になります。
もしA社とB社が同じ町内に2本の水道管を敷設したら、設備コストは2倍。誰も得をしません。
だからこそ、水道では「市場競争」ではなく「公共による統一管理」が合理的なのです。
こうした自然独占を前提に、地方公営企業法では、自治体が企業会計を採用し、経営の透明性と料金の適正化を図るよう求めています。
また、料金は地方議会の議決を経て設定されます。これにより、市民代表による監視機能が働き、過度な値上げを防ぎつつ、持続的な更新投資を担保します。
つまり、公営は“非営利”ではなく、“公共目的のための経営”なのです。
5. 公共性・安全保障の視点:止めてはいけないインフラ
水道は「止めてはいけない」インフラです。
災害時や感染症流行時でも供給を続けるため、自治体は防災計画や耐震化を進めています。
民間企業は採算が合わなければ撤退できますが、水道は撤退できません。
離島や山間部など採算が取れない地域にも配管を延ばし、同じ料金で供給する。これが「費用平準化」という公営の使命です。
料金を低く抑えすぎれば更新投資が滞り、結果的に将来のリスクが高まります。
“いまの安さ”と“将来の安全”のバランスを取ること――それ自体が行政責任なのです。
6. 具体例:東京都水道局と世界の再公営化の流れ
東京都水道局は、典型的な公営モデルでありながら、高い効率性を誇ります。
一部業務は民間委託していますが、資産と料金決定権は都が保持し、「運営の効率化は民間に」「責任は公に」という分担を実現しています。
一方、海外では1990年代に進んだ民営化が、近年は**再公営化(Remunicipalisation)**へと戻りつつあります。
フランス・パリでは料金上昇と情報の不透明さを理由に公営に戻しました(出典:TNI『再公営化という選択』日本語版PDF)。
また、日本語で整理された事例として「世界の水道再公営化にみる 公共の再生(全労連報告書)」も参考になります。
結局のところ、どの国でも“水の経営”には「信頼」が欠かせません。
それを最も安定的に担保できるのが、公共の仕組み=公営なのです。
7. よくある誤解と現実
| よくある誤解 | 実際のところ |
|---|---|
| 公営は非効率 | 企業会計導入で経営指標を可視化。むしろ監査体制が厳しい。 |
| 民営化すれば安くなる | 短期的には可能でも、設備更新が滞ると長期的コスト増。 |
| 公営は税金で支えられている | 水道は独立採算。料金収入で運営。 |
| コンセッションは民営化 | 実際は「運営権」の委託であり、資産は公有のまま。 |
8. まとめ
水道事業が公営であるのは、制度的な偶然ではなく、合理的な選択です。
衛生・安全・公平・持続性――これらを同時に満たすためには、短期的な利益ではなく長期的な信頼が必要です。
民間との協働(PPP/PFI)はこれからも進みます。
しかしその根幹に「公共の責任」がなければ、水道の価値は守れません。
蛇口の向こう側には、静かに社会の信頼が流れています。
その流れを絶やさないために、公営という仕組みが存在しているのです。
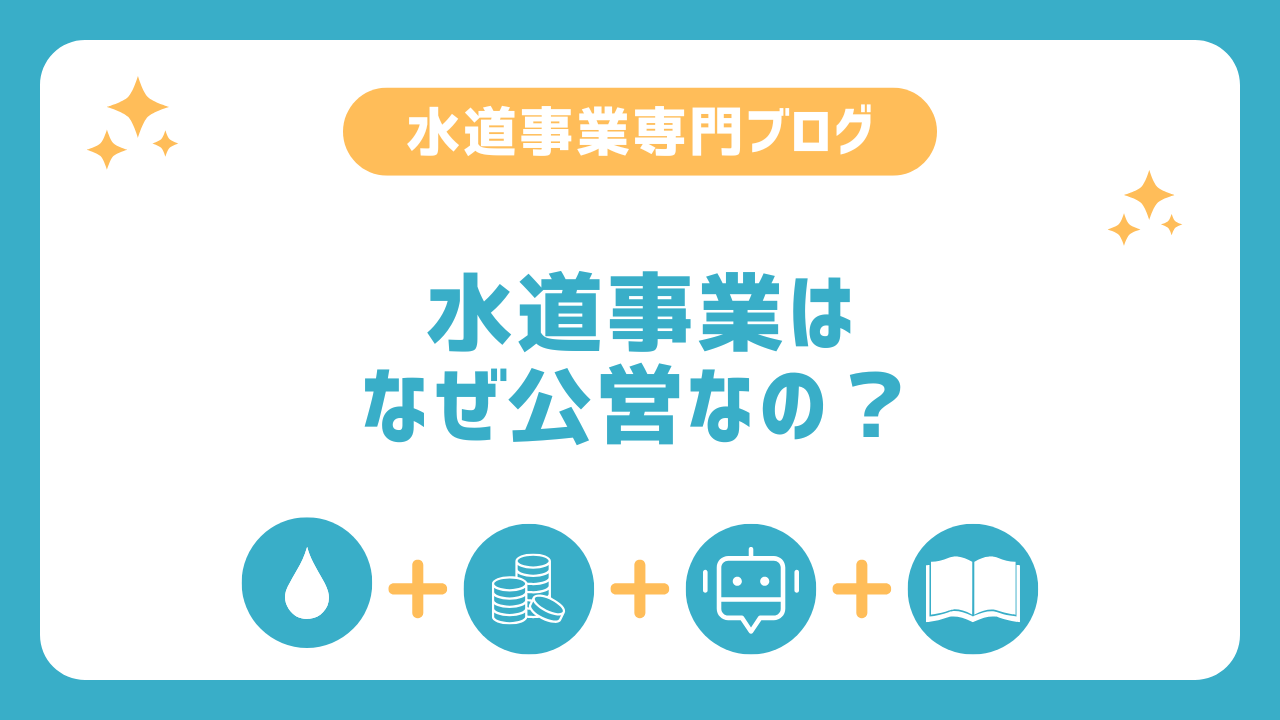


コメント